突然の脳梗塞は、私の仕事・家庭・日常生活すべてに大きな変化をもたらしました。入院初日からリハビリ開始、社会復帰に向けての退院後の運転再開の手順、私がどのように乗り越えてきたのか、誰にも話せなかった不安・苦悩・小さな達成感なども包み隠さず、実体験をもとにお伝えします。
孤独や不安を感じた瞬間もありましたが、支えや工夫で乗り越えた体験をまとめました。家族との対話や、モチベーション、これから回復を目指す方の参考になるよう本音で書きました。
※医学的な助言ではなく体験談です。方針は必ず医師にご相談ください。
入院生活
突然の発症・入院初日
発症当日は突然の体調異変があり、家族に連絡して自分で病院へ。診断後は即入院となり、体力・気力ともに最小限の状態でベッドに横たわることに。
「今日から点滴と絶食です」と告げられ、最初は戸惑いもありました。しかし、看護師さんが24時間体制で見守ってくださり、万一の対応も整っていることを知り、次第に安心感を持てるようになりました。病棟では他の患者さんが医療器具を使いながらも懸命にリハビリに励んでいる姿が印象的でした。
他の患者さんの中には排尿管理のための医療器具を使用されている方もおり、処置時の不快感について話されていました。「自分はまだ動けるだけでもありがたい」と思うようになりました。
心電図 セントラルモニター
入院中は心電図・血圧管理が徹底されており、異常が検知されると、看護師さんが様子を確認に来てくれます。「血圧が上がっていませんか?」と常に気を遣ってもらうことで、体調管理と安心を両立。改めて病院スタッフの細かな心遣いに感謝した日々でした。
入院中の日常と考え方
入院中の生活・家族とのやりとり
入院生活で一番の支えとなったのは、毎晩の家族との電話でした。体調の報告だけでなく、その日の食事やリハビリの進み具合を伝えることで、自然と会話のリハビリにもつながり、前向きな気持ちを維持する助けになりました。
家族からの厳しい言葉や励ましが、孤独な入院生活も前向きに過ごせる原動力になり、更に、このことが退院後の生活習慣をも見直すきっかけになりました。
楽しみ!
最初は、寝れることが喜びでした。だけど2日で飽きてしまい、いろいろなことが頭の中を駆け回るんですが、絶食後の食事が楽しみで仕方ないんです。睡眠が満たされると次は食欲が出てくるんです。頭の中は、食べたいメニューが次々に浮かんでました。
現実
絶食の後はおかゆからスタートしました。最初は味の薄さに物足りなさを覚えましたが、食事ができること自体がありがたく、数日も経つと「今日はどんなメニューだろう」と楽しみに思えるようになりました。
認識
私は周りの方と違い自分から専門の脳神経外科に行ったため、今どこにいて自分がどうなっているのか認識していたため、パニックに陥らず早く治して日常生活に戻ることしか考えていなかったことが思い返すと凄く良かったのかもしれません。

リハビリの始まり・専門療法士による訓練
4日目から本格的なリハビリスタート。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の3名が連携して、それぞれの目標を設定してくれました。
歩行練習やバランス感覚の訓練、手指の動きを取り戻すトレーニングなど、思うようにいかないことも多くありました。しかし、一歩ずつ進めることで小さな成長を実感でき、その積み重ねが大きな自信につながりました。最初はできなくても「成長できる」と実感できる時間でした。
理学療法では、まず歩行練習からスタートしました。手すりがある場所を使ってまっすぐ歩く練習や、バランスを保つ訓練を繰り返します。以前は当たり前にできていた動作が難しくなっていることに驚きました。
作業療法とは、左手腕のテーブル上での物品操作や手指の巧緻性訓練でした。どのくらい左手や指が動くのか物をつかんで移動できるかを行いましたが、全然できませんでした。左の握力を図ってみると10キロ少しで左指の細かい操作が全然できませんでした。
言語聴覚療法については、言葉がもつれなく喋れたため3回ほどの確認で済み、その時間を理学と作業に振り分けられました。
先を見据えて
理解しているつもりでしたが、いざ動かそうとすると左半身の機能、手腕足が電池が切れてしまったように動かなくなっていました。ただ、私は気絶することなく病状の進行を体験し、気が付いたら突然動かなくなっていた訳ではないので、冷静な自分でいられたのが大きかったです。
脳梗塞後は家族と過ごす時間の大切さを改めて実感しました。自宅では家族のサポートが必須で、職場復帰も時間をかけて進めました。また、退院後は趣味の週末のドライブなど「日常の喜び」を再発見し、体力・気力の回復にも役立ちました。
療法士さんから何度も聞ききましたが、「感覚を戻すには1か月から3カ月間は特に戻しやすいゴールデン期間で、さらに約半年間は戻っていく可能性があり、その後も緩やかですが少しづつ回復される」と、このことは自身のモチベーションに拍車がかかりました。
そこで、ベットに戻っても訓練ができる様にそれぞれの療法士にリハビリ道具はないか、聞いたところ、握力を回復させるために紙とテープで簡単なボールと紙の棒を作っていただき、ベット上で暇な時間にボールを握り、棒を横に持ち負荷をかけたりと握力と腕力の回復に努めました。

手腕の機能の評価
点滴が無くなってから、ボードなどを使った作業試験みたいなことを行いました。実はこれ、物をつかむ、運ぶ、つまむなどの日常生活動作の遂行能力の点数化でした。基本的に健康体の方で100点満点中96点以上となるそうですが、私の場合、最初28点だったと記憶しています。
その後、転院する2週間の最終日に60点まで取れるになっていました。点滴終了後、手腕ともに急激に動かせるようになってきましたが、まだまだ日常生活には不十分でした。
服のボタンを留めることが出来なく、服の着脱が難しくなったことで、自分の変化に戸惑いを感じましたが、少しずつできることを増やすことで前向きな気持ちを取り戻していきました。
片足で立って、どれくらいの時間バランスを取ることが出来るか、片足立ちでボールをキャッチできるか、真っすぐに歩けるか、30メートルを何秒で歩けるかなど。手や腕だけではなく、日常生活を送るための身体能力の訓練を行いましたが、最初は全くできなく気持ちは最悪でした。
療法士さんから聞いたのは、「脳の回路が切れてしまいリハビリや日常生活で新たな迂回路を構築していき、また動かせるようにしていくんですよ」と、早い期間には構築しやすいのでリハビリが必要なんですと。もちろん、その後も日常生活の為リハビリが必要な場合もありますと。
退院後、運転再開の手続き
退院が近づくと「運転再開」の話に。実は脳梗塞経験者は必ず運転免許センターで相談し、医師の診断書・必要に応じて運転シミュレーター検査などの手続きが必要です。
運転再開を希望する場合は、まず住んでいる都道府県の運転免許センターや試験場に連絡し「安全運転相談」を受けます。必要に応じてドライブシミュレーターによる検査や、医師の診断書の提出が求められます。安全のための大切な手続きなので、早めに情報を集めることをおすすめします。
更に詳しく聞いたところ一番早くて楽なのは、ドライブシミュレーターがあるリハビリ病院に転院し検査を受け、医師に診断書を書いてもらい提出し、公安委員会から「運転再開の許可を得ること」が必要ですと聞きました。
【まとめ】
私の体験から、早期のリハビリ開始と家族・医療チームとの密なコミュニケーションが回復の鍵だと感じます。社会復帰の道のりは決して平坦ではありませんでしたが、「今日できたこと」を積み重ねていくうちに、前向きな気持ちを取り戻すことができました。
小さな達成を大切にすることが、回復への近道だと実感しています。これからリハビリに挑戦する方、家族のサポートをする方へ、ぜひ小さな成長を大切に積み重ねてほしいと思います。
本記事が少しでも希望やヒントになれば幸いです。これからリハビリを始める方は、無理のないペースで毎日の小さな変化を積み重ねることが大切だと思います。私の体験が、少しでも前向きな気持ちを持つきっかけになればうれしいです。
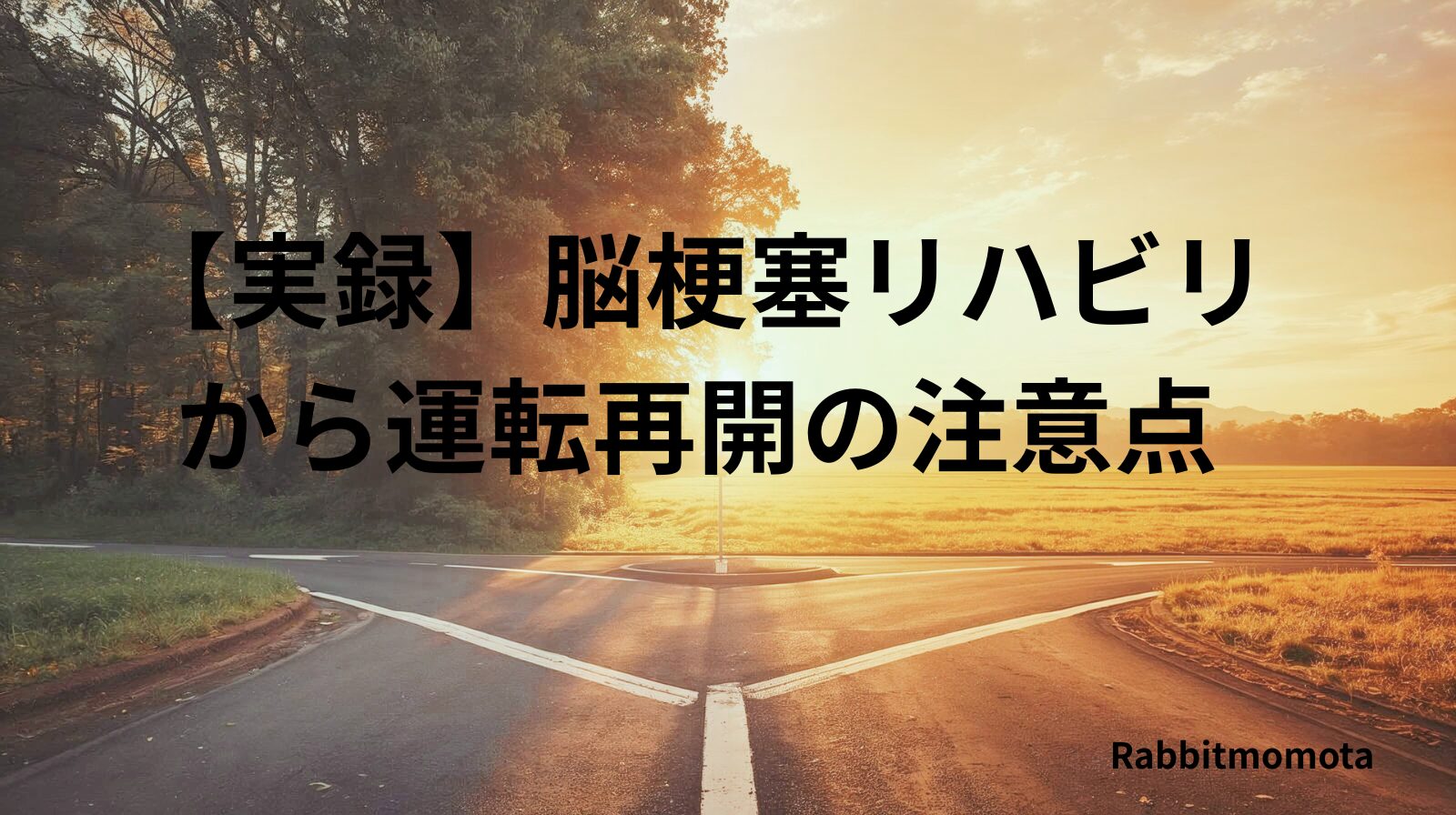


コメント