脳梗塞は、私の人生を大きく変えた出来事でした。
発症したあの日、突然左手に力が入らず、言葉が思うように出てこない――。その瞬間、体の異変と共に心の中にも冷たい衝撃が走りました。
病院のざわめき、真っ白な天井、医師の説明。どれも現実感がなく、遠い夢のように感じました。「普通の一日」が一瞬で消え去り、「これから自分はどうなるのだろう」という不安と恐怖が押し寄せたのです。しかし同時に、当たり前だった日々の尊さを深く実感した瞬間でもありました。
こうして始まったのは、“新しい自分と向き合う日々”です。身体のリハビリだけでなく、心の再生も必要でした。この記事では、私が3年半かけて心と向き合い、日常への帰還を果たすまでの実践記録をお伝えします。
医療的な判断ではなく、あくまで一人の体験談として。
同じような経験をされた方の心が、少しでも軽くなるきっかけになれば幸いです。
脳梗塞後に起こる心理的変化とは
感情の不安定さと抑うつ傾向
脳梗塞の影響で、感情の起伏が激しくなることがあります。
私自身、発症後は理由もなく涙が溢れたり、些細なことで苛立ったりすることが増えました。まるで自分が自分でなくなったような感覚に襲われ、「なぜこんなに心が乱れるのか」と悩む日々。
そんなとき、先生から「それは性格の変化ではなく、脳の回復過程で自然に起こること」と説明を受け、少し心が救われました。感情の波は異常ではなく、脳が回復しようとする自然なサインなのだと気づけたことが、心の支えになりました。
自尊心の低下と社会との距離感
退院後の生活は、思っていた以上に小さな壁の連続でした。
シャツのボタンを留める、食器を洗う――そんな日常の動作でさえ時間がかかり、何度も「以前の自分」と比べては落ち込んでいました。
仕事に復帰できるのかという不安、友人との会話で感じる距離感。「社会から離れてしまったのではないか」と感じたこともあります。それでも、リハビリの先生が言ってくれた「焦らず“できること探し”をしましょう」という言葉に励まされました。
家族が「昨日より上手にできたね」と声をかけてくれたことで、「今の自分も悪くない」「できるようになりたい」と思えるようになりました。こうした小さな気付きが、再生への原動力になっていったのです。
小さな「できた」を積み重ねる日々
リハビリで大切にしたのは、「完璧を目指さない」ことでした。
朝起きて顔を洗う、散歩をする、それだけでも「今日も一歩前進できた」と考えるようにしました。
過去の自分と比べるのではなく、「昨日の自分より今日の自分を少しでも好きになれるか」。この意識の転換こそが、心の回復を支える大切な鍵でした。
リハビリ病院での「はじめの一歩」
リハビリ専門病院へ移った初日、ベッドの端に座るだけで頭がふらつき、体の力が抜けていくようでした。動くたびに現実を突きつけられるようで、思わず涙が滲みました。
自分でトイレに行くことすら許されず、看護師さんに手を貸してもらう度に、情けなさと申し訳なさで気持ちが沈むのを止められませんでした。
でも、ある日、トイレに一人で行くことに許可されました。外の日差しや遠くの木々が視界に入った瞬間「また一歩前進した」と心に灯がともる気がしました。ささやかな前進を担当の療法士さんと一緒に喜ぶことで、自分は一人じゃないと実感でき、再生のスタートを踏み出せた気がします。
認知機能の変化と混乱
最も苦労したのは、記憶や判断力の低下でした。
言葉が出てこない、予定を忘れてしまう。そんな自分に戸惑い、無力感を感じた時期もあります。
しかし、脳には「新しい神経回路を作る力」があると知ってからは、焦る気持ちが少しずつ薄れていきました。携帯にその日の出来事をメモする習慣をつけたことで、徐々に混乱が落ち着いていきました。

心理的変化に対する対処法
医療スタッフや家族との対話
心が沈むときは、一人で抱え込まずに人と話すことを意識しました。「悩みを紙に書き出す」「週に一度相談する」「療法士さんに3日ごとに気持ちを報告する」。これを続けるうちに、自分の気分の変化に気付けるようになり、心の波を客観的に受け止められるようになりました。
家族や仲間の支え
家族の存在は、何よりの支えでした。妻の「今日も頑張ったね」という言葉や、病院で知り合った仲間との励まし合いが、心に大きな灯をともしてくれました。同じように努力している仲間の存在が、「自分ももう少しやってみよう」と思える原動力になりました。
自己肯定感を取り戻すための工夫
「昨日よりも前へ進むこと」。
これが私のリハビリの合言葉でした。たとえ一段の階段を上るだけでも、それは確かな進歩。療法士の「今日は一段でも上がれたね」という言葉が、何度も私を支えました。
できたことを記録し続けることで、少しずつ自信が育ちました。スマホのメモには「左手でお椀を持てた」「歩行距離が伸びた」など、ささやかな成功を積み重ねました。
それを振り返るたび、「自分は確実に前に進んでいる」と実感できたのです。
再発への不安と向き合う勇気
脳梗塞を経験した者にとって、再発への不安は常につきまといます。私も血圧の数値が高いだけで不安に駆られたことが何度もありました。けれども医師から「不安を感じるのは自然な反応」と教えられ、恐れるのではなく“準備する”意識へと切り替えることができました。
食事・運動・睡眠の管理を徹底することで、心の安定も取り戻せるようになりました。
そして今では、「明日を恐れず今日を大切に生きる」ことが、私の生き方の軸になっています。

心の安定を支える生活習慣
規則正しい生活と睡眠の質向上
規則正しい生活を心掛けることで、心の落ち着きを取り戻しました。朝のストレッチや血圧チェック、就寝前の音楽や読書。スマホを見る時間を減らすだけでも、睡眠の質が大きく改善されました。栄養バランスを意識した食事を家族と一緒に工夫することも、回復の支えになりました。
退院後は趣味の時間を大切にしました。音楽鑑賞や家庭菜園、近所の散歩。
オンラインで仲間と話す習慣も続け、社会とのつながりを保つことが心の安定につながりました。
友人との再会で感じた「自分の居場所」
しばらく外出を控えていましたが、退院後2か月が経った頃、勇気を出して旧友たちとカフェで集まりました。みんなの会話のテンポや話題についていけるか、とにかく不安で心臓がドキドキしていました。
実際あいさつの言葉がうまく出なかったり、記憶が曖昧で話の途中で混乱したり…。
でも、友人の一人が「できなくなったことより、こうやって”一緒にいられること”が大事だよ」と優しく声をかけてくれたのです。
その一言に救われ、楽しい時間を少しずつ心から味わえるようになりました。
“できること”を数えるのをやめ、“今ここにいる自分”を受け入れる大切さに気づいたひとときでした。
復職初日の緊張と、ひとつの変化
職場復帰の日、玄関のドアの前で動悸が止まらず、深呼吸を十回以上してから足を踏み出しました。パソコンのキーボード操作すらおぼつかず、思考のスピードが以前よりも落ちている自分に何度も焦りを感じます。
けれど周囲の仲間は、「何かあれば声をかけて」とさり気なくフォローし、仕事の分担も自然に調整してくれました。「頼ることは恥ずかしいことじゃない」そう心が切り替わった時から、少しずつ仕事の楽しさが戻ってきたのを実感できました。
趣味や交流による気分転換
退院後には、音楽鑑賞、家庭菜園、近所への短い散歩など、「心が安らぐ瞬間」を意識的に作るように心掛けました。
家族や仲間との週に一度オンラインで交流をする習慣を作り、外の世界とつながる安心感を感じる重要なひとときとなりました。仕事復帰後は、職場の仲間との会話やSNS閲覧も心の安定につながりました。
自分と対話する静かな時間
退院後、毎晩寝る前に携帯に今日行ったことを書く習慣を始めました。
一日の中で「できたこと」や感じたことを書き出すことで、不安や焦りが少しずつ和らいでいくのを感じました。
“今日は部屋を少し片づけた”“近所のスーパーまで歩けた”…そんな小さな一歩の積み重ねが、少しずつ心の明かりを取り戻すきっかけになりました。「心のリハビリ」は目に見えませんが、こうした小さな自己対話が、自分自身を再生させる大きな力になるのだと気づくことができました。
体験談:揺れる心と前向きな一歩
発症から3年半。
夜眠れない時期もありましたが、「焦らず自分のペースで歩けばいい」という言葉に支えられて、少しずつ前を向けるようになりました。
料理や家事を再びこなせた日の喜び、車のハンドルを握れた日の感動。
その一つひとつが、人生の再出発を実感させてくれました。
まとめ:心のリハビリも回復の大切なプロセス
脳梗塞からの回復は、体だけでなく心のリハビリも大切です。
焦らず、比べず、諦めず。その三つを意識しながら、家族・医療スタッフ・仲間と共に歩むことで、必ず心の中に“前へ進む勇気”が育っていきます。
発症から3年半経った今も、完全に元通りとは言えません。
それでも、“今の自分を受け入れ、今日できることを続ける”ことで、以前よりも穏やかで豊かな時間を過ごせるようになりました。
この体験が、今まさに回復の途中にいる方へ、静かな勇気と希望を届けられたら嬉しく思います。
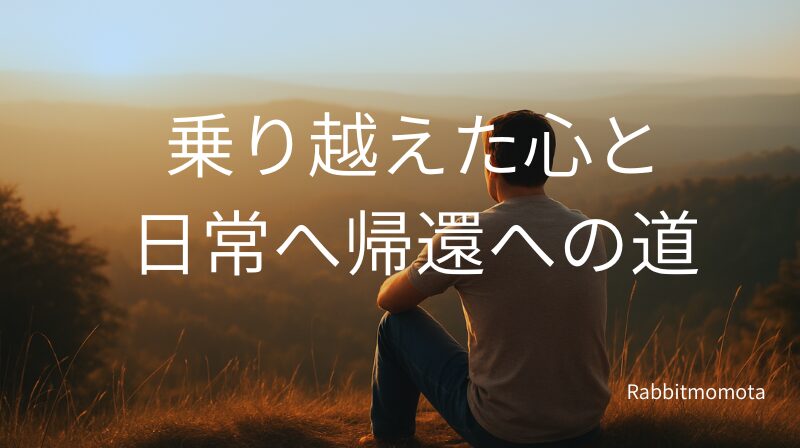
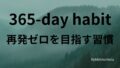

コメント