脳梗塞を発症した私は、治療後にリハビリ病院へ転院し、社会復帰を目指して日々を過ごしました。初めてのリハビリ病院での入院生活には不安がありましたが、スタッフや同じ立場の仲間との出会いが私の支えとなりました。
この記事では、私自身が経験したリハビリ病院での生活、心境の変化、退院後の変化を通して、「回復までのリアルな日常」をお伝えします。
※ここでの内容はあくまで私個人の体験です。同じ状況の方の参考になれば幸いです。
リハビリ病院での新しい日常
リハビリ病院での初日、見慣れない設備やルールに戸惑うことも多かったのですが、次第に病院での生活サイクルに慣れ始めました。特に食堂での食事は、唯一皆と顔を合わせる時間でした。
私は最初、とても緊張して無口でしたが、隣の席の方が「昨日より指がうまく動いた」と笑顔で話すのを聞いて、自分も頑張ろうと思うようになりました。入院当初は孤独や不安ばかり考えていましたが、今では明日のリハビリや仲間との進歩報告が生活の中心になっています。
さらに、看護師さんや療法士の方々が定期的に「困っていることはありませんか?」と声をかけてくれるおかげで、安心して治療に専念できる環境が整っていると強く感じます。
お互いの小さな進歩を喜び合ううちに、孤独感がやわらぎ、「一緒に頑張ろう」という前向きな気持ちが芽生えました。そうした交流の時間が、リハビリへの大きな励みになりました。
周りの方々の努力を見て、「自分も頑張らないと」と思えるようになり、入院生活の中でも前向きな気持ちを保つことができました。明るい空気の中で過ごす毎日は、リハビリそのものを支える大切な時間になっていました。
仲間から学んだ前向きな姿勢
同じ病院で出会った仲間には、高齢の方から30代の方まで幅広く「自分の目標」を持って努力している方が多くいました。
例えば、ある70代の男性は「孫の運動会に自分の足で参加したい」と毎日歩行訓練に励み、若い女性は「退院したら料理を再開したい」と調理台の前で細かな指の動きを練習していました。
私はそうしたみんなの姿を見て、「完璧じゃなくていい、焦らず今日できることをやる」ことの大切さに気付きました。自分1人では気が遠くなる作業も、皆で「できた!」と喜び合えることで心身ともにポジティブになれます。
私自身も、入院開始時にできなかった「左手で水が入ったコップをこぼさず持つ」ことが、できた時には大きな自信につながりました。誰もが自分のペースで少しずつ回復を目指し、できることを一つずつ取り戻していました。
その光景が私の励みになり、「焦らず続けていこう」と前向きな気持ちを持てるようになったのです。退院を目指す人、生活の自立を目指す人、それぞれが目標を持って努力していました。
私もまた、できることを増やすたびに小さな喜びを感じ、その積み重ねが日々のモチベーションになっていきました。

リハビリで変わる毎日
リハビリの毎日は、身体機能回復だけでなく「自分らしさを取り戻す挑戦」の連続でした。最初は腕や手指の細かな動きが思うように動かせず、何度も泣きたくなりました。しかし担当療法士の先生が「昨日より5秒も長く片足で立てただけでもすごい進歩ですよ!」と毎日声をかけてくれ、励まされました。
また、週に1回の評価日には、「腕の握力」「歩行距離」「できる動作」など数値で自分の成長を確認し、次の目標を自分自身で設定できるようになりました。今では朝のストレッチや自主訓練が日課となり、徐々に自分自身を認められるように変わりました。
自分の努力が数字や実感に表れることで、リハビリの辛さより「回復の手応え」が大きくなり、毎日を前向きに過ごせるようになりました。
入浴と食事で感じた「普通の幸せ」
リハビリ病院では週2回の入浴日があり、スタッフさんが見守り安全が確保されている中で入浴します。湯船に浸かるたび、リハビリや検査でガチガチだった筋肉がゆるみ、心もふっと軽くなる感覚を覚えました。また、食事は栄養士監修で塩分控えめ、野菜や出汁の味を大切にした献立が出ます。
私は糖質制限や減塩食など、退院後も自分でできる献立作りのコツを毎日教えてもらいました。以前は「好きな物を食べる」だけでしたが、今は「体が喜ぶ食事」を考え、食べることへの価値観が大きく変わりました。退院後も、病院でもらったレシピで家族と一緒に健康的な食事を続けています。
当たり前だった入浴や食事が、今では感謝の気持ちを思い出させてくれます。食事は健康を守る上で欠かせない要素であり、「食べること」への意識が大きく変わりました。今まで当たり前だった食事や入浴が、どれほどありがたいものかを改めて感じる機会になりました。
運転再開へのステップ
リハビリ後期には「運転再開に向けた訓練」として、病院の運転シミュレーターを使いました。最初はハンドルを握る感覚や左右の認識が鈍く、思うように操作できず何度も悔しかったです。
しかし、毎日少しずつステップアップし、例えば「左手を使った操作」「周囲の状況を予測し判断する」など細かな動作を繰り返し練習しました。安全のためのルールも定期的に学び、主治医やリハ担当者と相談しながら段階的に自信をつけていきました。
自分のペースで確実に練習し続けることで、退院前には「運転再開に支障ありません。」と判断いただき、大きな達成感を覚えました。
さらに、運転再開に向けては、身体機能だけでなく高次脳機能障害(注意力・判断力・記憶力など)の有無も欠かせません。私の場合、病院で行われた高次脳機能障害検査を数日にわたり受けました。
検査内容は多岐にわたり、想像以上にエネルギーを要するものでしたが「運転再開に支障なし」との診断書をいただき、ようやく再びハンドルを握る日が見えました。
失敗を繰り返しながらも、少しずつ確実に前に進んでいることを実感できるようになり、「諦めなければきっとできる」という気持ちに変わっていきました。

退院後の新生活と再発予防
退院の日、玄関を出て新鮮な空気を吸った瞬間に「これが再スタートだ」と実感しました。退院は終点ではなく「新しい生活への挑戦」だと受け止めています。
退院後は家の中での転倒や血圧変動も注意が必要なため、医師や栄養士、家族と連携しながら「生活リズムの見直し」「自宅ストレッチ」「献立内容の確認」を徹底し始めました。
とくに再発予防として「減塩」「適度な運動」「睡眠時間の確保」「定期血圧測定」を意識し、生活習慣の細かい見直しを続けています。退院後の今も、担当医との相談で新しい目標を立て直しながら「無理なく続ける」ことを大切にしています。
家族との関係の変化
退院してからは家族のありがたみや支えがさらに身に染みて感じられるようになりました。入院中は妻が毎日励ましてくれ、退院後も気づかってくれています。私は「家族に恩返ししたい」と思い、料理や洗濯など小さな家事にも積極的に行っています。
また、毎晩その日の体調や心の不安を妻に相談する時間を作り、「悩みは家族でわけ合う」ことが絆を深めるきっかけになっています。退院して初めて知った家族の優しさや協力は、私の最大の励みです。
まとめ:前を向く力は日常の中にある
脳梗塞発症からリハビリ、退院、社会復帰までの道のりは決して順調ではありませんでした。
ですが、苦労や不安、喜びや努力の日々が今では確かな自信と「自分らしい生活」につながっています。今後も健康・家族・周囲への感謝、そして「諦めない心」を大切に、日々を大切に過ごしていきたいと思います。
この体験記が、同じ境遇の方やご家族の方に少しでも希望や安心、そして回復へのヒントが届くことを願っています。「あきらめず、自分のペースで前に進む」ことこそが、回復への一番の近道です。
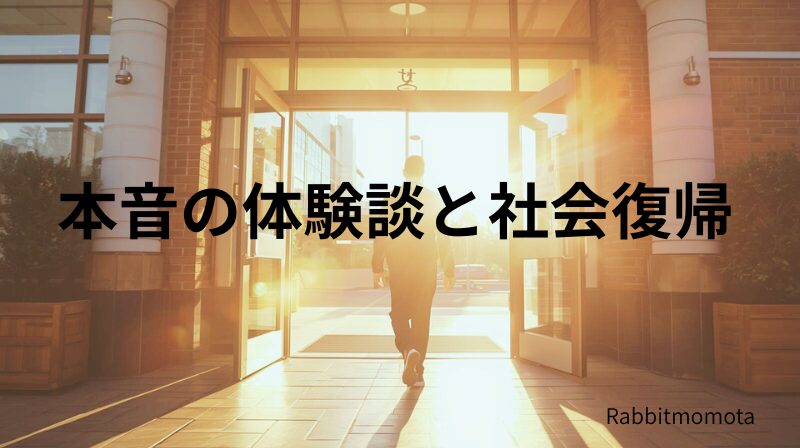

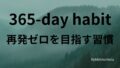
コメント